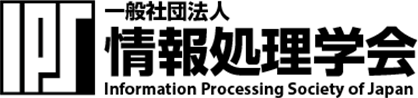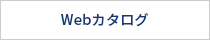産業界側の副会長を拝命してもうすぐ1年となります(情報処理学会では学術界・産業界から1名ずつの副会長を立てており、毎年交互に改選する形をとっております)。経営企画委員会をはじめとする学会全体の運営にかかわる取り組みや、各理事の担当範囲に収まらない課題への対応を、先任の松原副会長をお支えしつつ、自分が先任となる来年度に向けて引き継ぎつつあるところです。遡って2018〜19年度には技術応用担当の理事を務めさせていただきましたが、当時は任期終盤にコロナ禍が始まるまでは会議のたびに御茶ノ水の学会事務局まで足を運んでおりました。今はほとんどの会議がオンラインとなり効率的になりました。会議の前後に他の理事の方々とお話する糊代がなくなったこともあり、良くも悪くも、といったところでしょう。
このオンライン化の流れにも関連して、先日あらためて考えさせられることがあった、という話をさせていただきます。
自分たちが学んでいることが世の中でどう活かされているのか、産業界の現場での活用イメージを学生の皆さんに持ってもらいたい、ということで、大学でスポット講義の形で取り組みを紹介する機会をときどきいただきます。その一環で情報系に入学したばかりの1年生にお話する機会がありました。ありがたいことにたくさんの質問をいただきました。多くは講義内容に関するものでしたが、1年生らしい根源的なものもあり、私の所感もあわせて2つ共有させていただきます。
「インターネットは人類のためになると思いますか?」
直前の質疑で誹謗中傷やフェイクニュースといったトピックも出ておりそこから想起されたのか、あるいは、SNSの窮屈さとともに育ってきたデジタルネイティブ世代のもやもやもあったのかもしれません。私としての答えはもちろん「はい」ではありますが、その想いをどう言語化するのか、なかなか難しいものがありました。そこで思い至ったのは、毎年実施しているこの講義自体がここ数年オンライン・オフラインを織り交ぜていることでした。以前であればオンラインではなく休講だったことでしょう。また、今の私の管掌の組織でも、首都圏以外に移住して問題なく業務にあたっているメンバーが多くいます。コロナ禍という大きなインパクトを経て、社会の方が対応しインターネットの可能性が拡がった、いいかえれば、人間社会がまだまだ技術のポテンシャルを充分に引き出せていない、ということかと思います。
「中高生に情報教育が進むことをどう思いますか?」
中学のころの経験がきっかけで情報系を志したとのことで、非常にうれしく思いました。情報処理学会の一員としては、こうした人材が増えていってくれればと期待します。私の世代では国内で1学年が200万人くらい、それが今では半分くらいになっています。国際的に競争が高まっているこの領域で、より多くの専門人材が求められるなか、今はまだ少ない女性も含め多くの方々に興味を持っていただきたいところです。
一方で、専門以外の人材の裾野が拡がっていくことも重要です。先日、nihuBridge
☆1(人間文化研究機構による研究資源のデジタル共有サイト)の活用の一環として小中学校で授業に活用している、という話を伺いました。文系・理系といった色分けが始まる前の世代に、人文系のコンテンツが、デジタルで届く、というハイブリッドぶりに大変感銘を受けました。1つめの質問でふれた、社会が技術を使いこなしていく、という観点からも、こうした取り組みが数年後数十年後に漢方薬のように効いてくることを大きく期待しております。
☆1 https://www.bridge.nihu.jp/