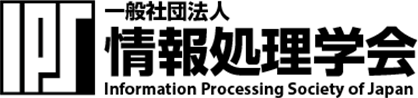「震災から学ぶ「情報」の再考」
西尾 章治郎(本会副会長)
本年3月6日から8日まで東北大学川内キャンパスで開催された第75回全国大会に組織委員長として参加した。未だ記憶に新しい、また、絶対に忘れてはならない東日本大震災を体験された方々から当時の状況を伺い、今後の情報社会を考えることを念頭に「ここから始まる情報社会の未来」と題した大会であった。その期間中、3月7日の午後を通じて、日本学術会議情報学委員会(筆者が委員長を務めている)の環境知能分科会との共催で、「情報をライフラインに」と題するシンポジウムが開催された。このシンポジウム開催は、本全国大会のプログラム委員長であり、環境知能分科会委員長でもある石田亨教授(京都大学)、実行委員長の亀山充隆教授(東北大学)、プログラム副委員長の木下哲男教授(東北大学)のご尽力に負うところが大きい。
本シンポジウムは2件の招待講演、2部にわたるパネル討論が組まれるという、内容の濃い構成であった。特に、筆者は、パネル討論の第1部「震災時の情報伝達を振り返る」と題するセッションでの東日本大震災当時の生々しい体験談には、涙を禁じ得ない程の感銘を受けた。その体験談において再三強調されたことは、災害時における安否確認の困難さであり、たった2文字の「ぶじ」という返信メッセージがもつ計り知れない大切さであった。この2文字が、どれだけ大きな安堵感と元気を与えたことか、改めて認識した。
私達は、1秒間に1京(10の16乗)の演算回数を実現するスーパーコンピュータ、あるいは世界中に蓄積・流通しているゼッタ(10の21乗)バイトという超大量のデジタル化されたデータを話題にし、「いつでも、どこでも、だれとでも」文字、音声データのみならず、画像データまでも送受信できる環境に既に慣れ切ってしまっている。なお、ここで敢えて「情報」と「データ」という言葉を区別して用いていることに留意いただきたい。
極限状態における「ぶじ」の2文字の重要さ、他方では氾濫するデジタルデータの真っ直中にいる現況を対比しつつ、筆者の頭の中では「情報」とは何かということへの再考がパネル討論会場で始まっていた。
「情報」という日本語については、明治期の森鴎外による訳語という説もあるが、実際にはそれよりも古く、1876年出版の訳書『佛國歩兵陣中要務實地演習軌典』において、仏語 “renseignement”の訳語として「敵情を報知する」意味で用いられたのが最初であるといわれている。これは、中国語における「情報」の意味が諜報活動を意味していることに近く、英語における“intelligence”に近い意味をもっていた。
ところが、電気工学者として著名な関英男が1954年に“information”の訳語として「情報」を採用し、それが広まることによって、「情報」という言葉の意味に一大変革が起きたと言ってもよい。興味深いことに、1948年に発表された、クロード・シャノンのInformation Theoryは、当初は情報理論と呼ばれておらず、Information は「インフォーメーション」とカタ仮名書きされていた。現在に至るまでに、「情報」という日本語は、英語の“information”の訳語という範疇を超えた、より広範で独特の意味をもつ言葉になってきたように思える。
このように「情報」のもつ意味が進化し続けている状況において、その本質とは何かを探求し続けることは緊要の課題であると考えており、その「処理」に深く携わっていくコミュニティである情報処理学会としても、常に問い続けなければならない課題であることは確かである。
過去半世紀以上にわたって「情報」のもつ意味は拡大してきたが、その本質を探求する過程において、私達が遭遇するすべての事象のなかで「情報」がまったく関わりをもたないと考えられることを列挙していくことも有効な手段であると思う。つまり、ある集合のもつ意味を明確にしていく過程において、その補集合のインスタンスを挙げていくような方法である。結果的には、ほとんどのことに「情報」が関わっているのが現代社会の特徴のように思えてならない。
近年、大学入学における情報分野への学生離れが問題にされて久しい。情報系以外の分野の先生方は、自分の分野を宣伝する際に、高等学校における教科「情報」の内容を巧妙に引用しながら、我が方に入学すれば、情報系で教えられていることは当たり前のように学習することができ、加えて、さまざまなものづくりに関わることができる、あるいは、わくわくするような実験ができる、などと説明して学生を勧誘される。このようなミスリーディングな方法によって、将来を担う有能な若い人材が情報分野から遠ざけられていることを知るにつけても、「情報」という言葉の新たな捉え方のコンセンサスを得て、それを広めていくことが喫緊の課題に思えてならない。